~戦時下の浄土真宗~
![]()
~戦時下の浄土真宗~
昭和13年に鐘楼ができたのですが、そのときの梵鐘が、それ以前から瑞光寺にあったものなのか、あるいはこの年に鋳造されたものなのかは分かりません。
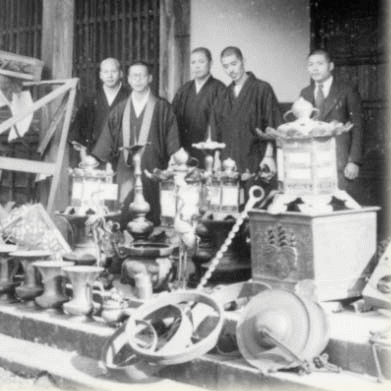 けれども、この梵鐘もまた、戦争中に「供出」という憂き目にあってしまいました。鋳直して武器や兵器に使うのだというのです。梵鐘だけではありません。喚鐘、大(だいきん)、輪燈に香爐や燭台、果ては鐃鉢(にょうはち)などの楽器に至るまで、とにもかくにも、金属製の仏具という仏具はみな供出させられたということです。
けれども、この梵鐘もまた、戦争中に「供出」という憂き目にあってしまいました。鋳直して武器や兵器に使うのだというのです。梵鐘だけではありません。喚鐘、大(だいきん)、輪燈に香爐や燭台、果ては鐃鉢(にょうはち)などの楽器に至るまで、とにもかくにも、金属製の仏具という仏具はみな供出させられたということです。
今でも本堂の物置に焼き物の香爐や華瓶(けびょう、中尊前で使う樒を立てる小さな花瓶)などが残っているのですが、それは、それらが 代用品であったということの証拠になるものでした。
代用品であったということの証拠になるものでした。
先年、敗戦50年を記念して「山陰教区全戦没者追悼法要」が行われた時に、記念事業として、「戦時下の浄土真宗」ということで写真展を開きました。教区内のあちこちのお寺に残っている戦争に係わる資料を提供していただいたものです 。その資料収集の役を仰せつかって東奔西走、200点ちかい資料を集めることができましたが、その中の50点ほどを選んでの写真展でした。今、手元に残っているものを見ても、仏教婦人会が戦闘機を献納したというものや、千人針、慰問袋を縫っているところの写真、国民の志気を高めるために催された「報国法要」の記録など、果たしてこれが…と思われるようなものがいくつもいくつもあります。
。その資料収集の役を仰せつかって東奔西走、200点ちかい資料を集めることができましたが、その中の50点ほどを選んでの写真展でした。今、手元に残っているものを見ても、仏教婦人会が戦闘機を献納したというものや、千人針、慰問袋を縫っているところの写真、国民の志気を高めるために催された「報国法要」の記録など、果たしてこれが…と思われるようなものがいくつもいくつもあります。
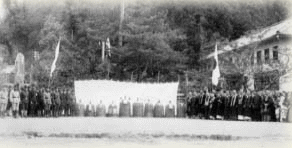 そしてもちろん、梵鐘供出、仏具供出の写真も複数ありました。多くのお寺では、ご門徒さんがたくさん集まって「お別れの法要」をお勤めになられたようです。中には、軍の関係者も集まって、いよいよ盛大に「お別れ式」が催されているものも見られます。
そしてもちろん、梵鐘供出、仏具供出の写真も複数ありました。多くのお寺では、ご門徒さんがたくさん集まって「お別れの法要」をお勤めになられたようです。中には、軍の関係者も集まって、いよいよ盛大に「お別れ式」が催されているものも見られます。
その中の1枚に、温泉津駅前に集められた梵鐘の写真があります。この写真は、役場庁舎移転に伴う資料整理の中、昭和18年の水害被害状況調査資料の中に紛れ込んでいたものと聞いております。「処分するのなら」と預かっておられた方から、回りまわって、 資料提供をいただいたものです。
資料提供をいただいたものです。
瑞光寺では、昭和17年10月4日に「お別れの法要」が勤められたようで、法要それ自体の写真は見当たりませんが、その日に撮ったという家族写真の裏書きに、そのことが記されています。梵鐘は供出されたまま、返ってはきませんでした。
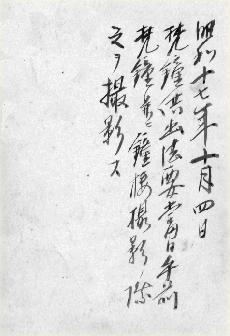 一方、喚鐘はというと、供出したとはいえ、近くの火の見櫓に架けられて使われていたそうです。しかし、叩き方が余りにひどかったのか、鐘はひび割れて使い物にならなくなってしまいました。それで、戦後になって火の見櫓が不要になったので、釜野地区にあった鐘をいただいて、それを現在も使っているという話です。戦後の物のない時のことです。喚鐘には、明治41年という日付を見ることができます。
一方、喚鐘はというと、供出したとはいえ、近くの火の見櫓に架けられて使われていたそうです。しかし、叩き方が余りにひどかったのか、鐘はひび割れて使い物にならなくなってしまいました。それで、戦後になって火の見櫓が不要になったので、釜野地区にあった鐘をいただいて、それを現在も使っているという話です。戦後の物のない時のことです。喚鐘には、明治41年という日付を見ることができます。
しかし、さすがに梵鐘の代用品はありません。戦後間もない頃に、復員された方から「高知の方に瑞光寺の梵鐘があった」ということを聞いて、前住職がご門徒と一緒に大急ぎで捜しに行ったのですが、発見することができず、行方不明のままです。
後日談ではありますが、実際のところは、武器や兵器になる前に敗戦となったので、結局、各地から集められた梵鐘や仏具の多くは、「鉄屑にされたらしい」ということでした。
しかし、中には数奇な運命を辿った梵鐘もあったようです。本願寺新報に「終戦記念日によせて」という記事がありましたので、転載してご紹介いたしましょう。
![]()
 カネを預かっています
カネを預かっています『本願寺新報』(2003年8月10日)