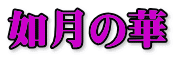 -九条武子ものがたり
-九条武子ものがたり
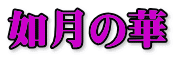 -九条武子ものがたり
-九条武子ものがたり
 来たる10月15日、九条武子さんの生涯を偲んで、前進座の特別講演が大田市民会館にて上演されることになった。
来たる10月15日、九条武子さんの生涯を偲んで、前進座の特別講演が大田市民会館にて上演されることになった。
瑞光寺からは約20名が観劇することになった。その案内、チケット販売をしていると、
「九条武子さんって、誰?」
「九条武子さんって、何をした人?」etc。
問われた私も、思い浮かぶのは「あそか病院」を作った人くらいで、武子さんのことは知らないに等しい。それで、事前学習をしようということになり、7月の安居会に合わせて研修会を開こうということになったのは、4月の仏婦総会の席上であった。
手元にある九条武子さんに関する資料は、大谷嬉子編『無憂樹(あそか)-九条武子全歌集』が1冊あるのみである。それも「積読」として買い置きしていたもので、殊に詩歌に疎い私には難敵で、あまり眼にしたくない分野のひとつ、斜め読みくらいはしたであろうが、内容についての記憶も曖昧である。
『無憂樹』には、九条武子さんがその生涯において書き残した詩歌1184首が収められている。昭和3年2月7日に往生の素懐を遂げられた武子さんは、歌集『金鈴』を大正9年7月に、随想集『無憂華』を昭和2年7月に発行されている。ちなみに、この『無憂華』が大ベストセラーとなり、その印税をもとに『あそか病院』が設立されたという。そして、没後の昭和3年11月に歌集『薫染』が、翌昭和4年12月に歌集『白孔雀』が発行されているが、これらの4作品から詩歌だけを集めたものが『無憂樹』なのである。
しかし、『無憂樹』に収められている詩歌や「略年譜」だけでは、彼女の生涯を捉えることができない。それで温泉津図書館に武子さんの生涯に関する書籍を探してもらうと、籠谷真智子さんと末永文子さんの著作があった。読み比べてみると、共通する事象は数々あれども、それぞれの視点が違っていて面白かったし、史料的にも詳しく調べておられて大いに参考になった。
これらを読み進めていくと、ベストセラーとなった『無憂華』は大正15年の1月9日から100回にわたって『読売新聞』に掲載された随想集であることがわかった。しかし、『無憂華』からの引用文の多くは、著者の意図により、その全文は掲載されていない。「中略」、「以下略」と述して省略されているのである。それは『無憂華』に止まらず、『書簡集』をはじめ、各書に及んでいる。
何故、それらの箇所が省略されたのか?
その省略の個所には何か書かれていたのか?
これは原本に当たるしかないと、再度温泉津図書館に無理な注文をお願いする。そして、昭和15年発行の『金鈴』と『無憂華』をお借りすることができた。『金鈴』は全くの詩歌集であったが、『無憂華』は随筆と詩歌の織り交ざったものであり、武子さんの思想や信念がうかがい知れる貴重なものであった。そして『薫染』『白孔雀』『書簡集』は今なお探索中である。


幼児のこころ ―九条武子著『無憂華(5)』
幼児が母のふところに抱かれて、乳房を哺くんでいるときは、すこしの恐怖も感じない。すべてを托しきって、何の不安も感じないほど、遍満している母性愛の尊き恵みに、跪かずにはおられない。
いだかれて ありとも知らず おろかにも
われ反抗す 大いなるみ手に(『無憂華』22)
しかも多くの人々は、何ゆえにみずから悩み、みずから悲しむのであろう。救いのかがやかしい光のなかに、われら小さきものもまた、幼児の素純な心をもって、安らかに生きたい。大いなる慈悲のみ手のまま、ひたすらに久遠のいのちを育みたい。
―大いなるめぐみのなかに、すべてを托し得るのは、美しき、信の世界である。
心の合掌―九条武子著『無憂華(100)』
ひるも夜も、うつろのなかに、永劫不変の存在をもとめようとしている。あわれ現世にあれば、頼るべきたづきもしらず、すべてのすがたの、あまりにも果敢なく消えてしまう、まぼろしを逐うて生きる因縁所生の地上には、誇るべき何物もない。かなしくも貧しき心を、いつわりの衣に秘めつつ、苦悩の闇路はるかに、疲れ切った歩みをつづけなければならぬ自分を、しみじみといとしく思う。
しかし、ありのままなる懺悔をささげて、つつましき合掌の心にかえるとき、迷えるもののために翳されてあった導きの炬が、瞭かにみつめられるのである。
おほひなる もののちからに ひかれてゆく
わがあしあとの おぼつかなしや(『無憂華』9)
如追憶の私から―九条武子筆『震災を顧みて』築地本願寺発行、大正13年8月
よろずみな そらごとなり 親鸞の
をしへまさしく 身にしみし夜や(補遺・籠谷20)
人もわれも 阿鼻叫喚の 地獄界
ただに譬喩と おもひてありき(薫染89)
因果経 それの絵巻を まなかひに
ひろげられしは 夢ならざりき(白孔雀124)
夢と思はば 覚めてぞ やすきまさごとは
胸に消がたき おもひでを彫る(白孔雀125)
かへさなむ ふるきにまさる 栄にと
いふ人の子 けふ力なき(拾遺Ⅱ26)
体験者の一人として再び去年のやうなことが繰り返されたらと思ふとき、自分の修養と覚悟のまだ足らざることが恥ずかしくなります。もうその時のやうな僥倖はたのめるとは思われませぬ、もし自分の周囲からすべてのものが再び失はれて、ただひとり取り残されたとしたら、家畜が猛獣のすむ原野にほふり出されたより以上に弱いものでせう。それとも恐らく大部分の女が少しも自覚なくして今日まで色々な保護の翼の下に安眠してをったといふことは考へなければならぬと思ひます。かの天災によりて自分の国がどれだけ痛手を感じてをるかを思ふたならば、静かに己の衣服をかへりみなければなりますまい。私はこの頃都市の中心街を歩いて見ますと、地震の体験者は一人もないのかと思ふほど旧に倍した華美な装ほひを見て云ひしれぬ感じがいたしますと同時に、親鸞聖人の『歎異抄』の言葉があの火に追はれてゆく道すがらひしひしと胸にきざまれました時を忘れてはならないと思ふてをります。
私共の短い一生のうちに第二の天災がどんな違った形でまた現れるかも知れないのです。宇宙の自然界には、我々人間の智慧できはめられてをらぬ不安がどれだけ潜在してをるかわかりませぬ。天災といふことがこの世の中の必然的のことであってみれば、その不可抗力の前にくづれてもくづれてもつみあぐるといふ不断の努力を平日に養っておかなければならぬといふ覚悟を必ずや多数の人が痛感されてをられませうことだけでも尊い体験であらねばなりませぬ。盛んに唱導されて居ります節約といふことも国益の奉仕として大切なことではありますけれども、それが消極的の節約でなく、もう一方には働いて得るといふことを忘れませぬ様にしたいものと思ひます。これは今後もつとつと女の方に自覚していただきたい第一で、これが地震から得た教訓であるとつくづくその感じを抱かされます。

最近の、一つの読書法として、パソコン入力をしながら「読む」という方法を採用している。
今回のように、九条武子の生涯にわたるデータを処理して研修会の資料作成が見えている時、昔は必要と思われる部分のみをデータ化していたけれども、研究なりデータ化を進めてみると、省いた所が再度必要になることがしばしばであった。
そして、その度に原本で探すのであるが、往々にしてその出拠の箇所が見つからないのである。ただいたずらにパラパラとページをめくって、時はむなしく過ぎるばかりである。親鸞研究しかり、才市研究しかりである。
ということで、今回も『武子研究』のために入力読書法を採用する。そして、それをPDF化して、『けんさく武子さん』となるのである。詩歌編、随想編と小分けにして、それぞれが「一発検索」できるし、あとはコピペして資料を作成すれば、その作業は実に楽チン。
ご希望の方にはデータをお分けします。ご連絡ください。