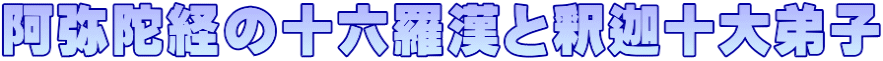
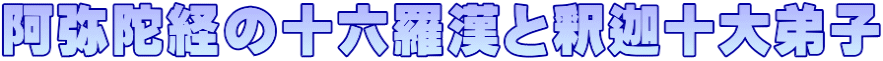
![]()
![]()
 (一)四姓平等の仏教
(一)四姓平等の仏教
哲学者の梅原猛先生が京都の洛南高校附属中学で行った仏教の13時間に及ぶ授業で、先生は、
「仏教がインドで生まれながらインドにおいて栄えなかったのは、カースト制度の抵抗があったからです。それに対して、釈迦はカースト制度を無視し、人間は皆平等だと言うのです。生きとし生ける者はみな平等というのが仏教の思想です」と。このことから考えて行くと、それをよく示しているのは十大弟子の一人優波離がお釈迦さまの故国カピラ国の王宮に仕える理髪師であったと伝えられていることである。カースト制度では最下層のシュードラ、奴隷に属した人である。
ある時、お釈迦さまが何度目かにカピラ国を訪ねられての帰路、その後を追いかける7人の若者の姿があった。そのうち6人はお釈迦さまの従弟の阿難陀を初め釈迦族の、しかも良家の青年。優波離だけが卑賤な身分であり、おそらく荷物持ちの役目だったのだろう。身分は生まれながらに決まり、生涯変えることができず、職業にも結婚にもそれぞれの制約があった時代に、この時、身分的に大きく違う7人が同時にお釈迦さまの許で出家したことは、階級制度を嫌い、人間の質を尊んだ教団の姿を如実に示すものと考えてもよい。しかも、入門によって、優波離は他の6人の上位に座した。
その経緯は幾つかの説があり、果たしてどれが真実か不明であるが、その二、三を紹介してみたい。
(二)優波離の出家
一つは、優波離が近道をして、6人よりもお釈迦さまの元に先着したという話である。
カピラ城から優波離と行動を共にした6人は釈迦族の境界を越えたところで身装具を取り外し、上着に包んで彼に渡し、「これを持って城に帰るように。これだけで今後は安楽に暮らせる」と、別れて帰国することを勧めたと言う。優波離はしばらく呆然としていたが、この時心中に、「恵まれた人々がこのように惜しげもなく地位も財産も捨てて出家してゆく。それほどまでに良い教えならば、自分もまた出家したい。」という願望が湧いた。そこで彼は受け取った包みを解いて傍らの木にかけ、空身でひたすら先を急ぎ、近道をしてお釈迦さまの元に先に着いたというのである。
優波離はお釈迦さまの許で授戒したいと懸命に願った。お釈迦さまはそれを快く受け入れて具足戒を授け、少し遅れて到着した他の6人に優波離を先輩として拝するように促したというのである。
*
優波離は先に行った6人を追いかけて合流し、共にお釈迦さまの元に辿り着いた。そして帰依するという念願が認められると、さて誰が一番先に授戒の儀を受けるかということになったという。この時、仲間の一人の跋提(バツダイ)が提案した。「家にいた時、私たちには驕慢の行いがあったが、優波離はそのような私たちに良く仕えてくれた。 出家の順は先ず優波離から。そうすれば、私たちは彼を先輩の比丘として敬い、合掌し、そのことを以てこれまでの驕りの心を捨てる証しとなるであろう。」と。
また、この授戒の順序はお釈迦さま自身の深い考えで決められたとする説もある。
ともかく、優波離は一足先に先輩の比丘となり、6人の三拝の礼を受けた。しかし、彼はそれを驕ることなく、終始実直に身を処して、お釈迦さまの四姓平等の根本精神を人々に覚らせる良き範となったのだった。
(三)優波離の修行
その当時、お釈迦さまも山頂での瞑想を好まれていたが、比丘たちの中には人気のない静かな林間や山上の洞窟などに住んでひたすら修行し、悟りへの道を求める人が多くいた。優波離がそういう修行を積みたいと願っても無理はなかった。
しかし、お釈迦さまは仰った。
「優波離よ、人里離れて住むことは淋しく、一人の暮らしには心の楽しみが得難い。時には自然の荒々しさに心を揺さぶられ、修業が進まない者もいる。優波離よ、そなたには荒野での修行は向かない。」と。そしてお釈迦さまは、「ここに池があるとしよう。そこに象がやって来て、気持ちよさそうに水浴びをする。それをウサギが見ていて、象の真似をして池に入った。しかし、水が深くて背が立たない。ウサギは怖くなって逃げ出した。だから人里離れたところでの修行もこれと同じで、向く人と向かない人がいる。そなたには相応しくない。」と。
優波離はこの譬えをよく理解し、教団にあって修行を続けた。何くれとなく比丘たちの面倒を見、事が起きると規律や決まりに照らして解決策を講じ、日常生活の中で悟りを開き、持律第一と呼ばれるようになったという。
(四)優波離の問答
『増一阿含経』には、次のような優波離の姿が載っている。
お釈迦さまが在家の信者が守るべき「八斎戒」の話をされたことがあった。これは在家の信者が一日一夜だけ出家したつもりで戒を守ることであり、その八つとは、
①生き物を殺さない
②盗みをしない
③性交をしない
④嘘を言わない
⑤酒を飲まない
⑥きらびやかに身を飾らない、歌舞を楽しまない
⑦高くゆったりしたベッドに寝ない
⑧昼以後、何も食べない
であった。すると優波離が、「それはいつ、どのようにして行えばいいのか」と質問した。お釈迦さまは「毎月8、14、15日に、沙門あるいは長老の比丘の許に行き、そこで朝から夜まで、阿羅漢のように一切を慈しんで修行しなさい」と、日時と方法を解説されている。
*
優波離はまた夏安居中に、とある精舎で争議が起きた時、それを解決してくれるようにと命じられたことがあった。
その時、彼は、「持って行くには衣が重く、かといって安居中の精舎に衣を置いて行けば、捨てる罪を犯すことになる」と、衣の処置を尋ねている。お釈迦さまが、「どのくらい日数がかかるか」と質問されると、「往復の2日ずつを入れて、計6日間」と答え、「6日ならば衣を手元から離してもよい」と許可を得て出発した。ところが、争議は期間内に治まりそうになかった。彼は一旦お釈迦さまの元に帰り、仔細を報告した。そこで、お釈迦さまは彼に一ヶ月の「不失衣白二羯磨(ふしつえびゃくにこんま)」、特別の場合には離衣を許す法を与えられた後、「衣を盗まれる心配がある時には、家の中に置いて良い」と、新たな決まりを作られたようである。
*
またある時、祇園精舎におられたお釈迦さまは、戒律の重要性を説かれ、このように戒律をきめ細かく守る優波離を賞賛された。そこで、多数の比丘が上座も中座も、下座も優波離の許へやって来て戒律を学ぶようになった。ところが、鼻つまみの行動が多い六群比丘は「比丘たちが戒律に詳しくなったら自分たちを誹謗することになるだろう」と考え、比丘たちに、「そのような細々した決まりにどんな意味があるのか。寧ろ疑惑や混乱に導くだけだ」と悪口を言った。これを聞いた比丘の一人が彼らを非難し、お釈迦さまに告げた。お釈迦さまは六群比丘を叱責された後、「学処を誹謗し、それを悔い改めなければ地獄に落ちる」という新たな波逸提法(はいつだいほう)、軽い罪を一つ制定されたとお経にはある。そのような中で優波離は信念を貫いたのであった。
(五)第一経典結集、「律蔵」のこと
お釈迦さまの入滅後3ヶ月が過ぎ、七葉屈で第一結集が開かれた時、司会役の大迦葉が先ず呼んだのは優波離の名であった。
そして、進み出た彼が、「何年の何月何日、お釈迦さまは是々の事件を解決するためにこういう定めを作られた。また、斯々の事件の時は、教団からの放逐も含めて、このような戒めを申し渡された」と、記憶に留めたお釈迦さまの戒律を述べ、一同が「その通り」と認めると、それが「律」となった。三蔵法師という言葉を聞くが、仏教聖典には「経」「律」「論」の三蔵がある。つまり、優波離は「律」の大元を作った人である。優波離が僧伽にいてくれなかったら、後世の「律」はどうであったろうかと思う。
第一結集後の優波離の動静は残されていない。(中村晋也)