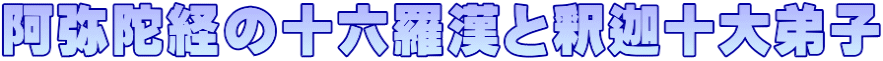
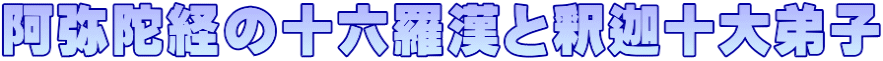
![]()
![]()
 (一)苦労に苦労を重ねた富楼那
(一)苦労に苦労を重ねた富楼那
富楼那は、故郷に帰って説法をしたいと願った時のお釈迦さまとの対話が有名だが、後の記録は少ない。
富楼那は、インド名はプールナ、一応ボンベイの北に位置するインドの古代貿易都市スナーパランタ国スッパーラカの出身とされている。父親は裕福な貿易商であったが、富楼那は父が召使の女性に産ませた子であり、両親の愛に恵まれずに育った。父が死ぬと、何一つ財産を分けてもらえずに家から出され、身一つで貿易の仕事に乗り出したと言われる。また一説には、実は長兄の妻と駆け落ちしたという話も伝わっている。
彼は境遇からして人の気持ちを見抜くのに巧であり、商才にも長けていたという。たまたま手に入れた香木で莫大な利益を得たという伝承もあるが、当時のインド貿易商人は、メソポタミア地方まで出かけて交易していたと言われる。荒れくれた男達をよく統率した彼は、やがて力のある商人に生長し、数年もするとひとかどの財産を築くに至っていた。
それは7度目の航海の時と伝えられているが、彼の商船に乗り合わせたコーサラ国舎衛城から来た商人たちが朝な夕な、何か歌のようのものを歌っていた。富楼那が訪ねると、「これは歌ではなく、仏陀の教えをこうして覚えているのです」ということだった。富楼那は概略を聞いただけで、お釈迦さまの教えの優れていることを理解した。
港に帰り着くと、即刻財産を整理して、全てを長兄に譲り、自分は身一つでお釈迦さまの許へと走った。この時、出家の願いが適っていた訳ではない。それなのに全財産を処分した。そこに彼の果敢な行動力を見る説と、余程心に重荷を抱いていたのであろうとする説がある。
そして舎衛城に着いた富楼那は、予ねてから貿易の仕事を通じて知っていた祇園精舎の寄進者スダッタ長者を訪ね、その紹介でお釈迦さまに会って教えを聞くことができた。そのまま念願通りに授戒して、お釈迦さまの教団の一員となった。
お釈迦さまの良き弟子となった富楼那は、何処にでも飛び込んでゆくおおらかさと、苦労をし尽くした人らしい、人の心のひだにも沁みるような話法で、多くの信者の信頼を勝ち得た。対機説法の名手のお釈迦さまに似た自由自在な語り口で、教えのツボを外さずに分かり易く説き、説法第一の称号を得るまでになった。
霊鷲山にいた富楼那の許へ、多数の外道の修行者がやって来たことがあった。外道たちは彼に「釈尊は有(生死を繰り返す迷いの世界)を断ち切れと説くのか」と質問をした。彼は「釈尊は有我の見解(変わらぬ自我は存在し続けるという考え)を断ずるように説かれる」と答える。外道たちが去った後、彼はお釈迦さまの許を訪れ、彼の説いたのが正しかったかどうかと伺った。お釈迦さまはこれを是認されたと『増阿含経』にある。
また、富楼那の弁舌が巧みなことは、後世日本にも伝わり、浄瑠璃の『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』に「富楼那の弁をふるい」という台詞があると識者に教えていただいた。
(二)殺されて本望と、故郷での布教
富楼那がお釈迦さまの教団に入って、どのくらい後のことかは分からないが、ある日、彼は姿を改めてお釈迦さまの前に進み出、故郷の町で布教に努めたいという決心を披瀝した。『阿含経』などにある、その一問一答が名高い。
「世尊よ、私は故郷のスナパアンダ国に帰って、そこで布教に励みたいと思います。どうか最後の教えをお説きください。」
「富楼那よ、あの地方の人は気が荒くて粗暴だと聞いている。もし人々がそなたを罵り嘲るような ことがあれば、どうするつもりか?」
「世尊よ、その時は、彼らいい人だ。手や棒で私を殴ったりしないと考えます。」
「では、手や棒で彼らが殴らなかったら、どう考えるか?」
「その時は、彼らはいい人だ。刀で私を傷つけないと思うことにいたします。」
「では、刀で彼らが切りつけたらどうするか?」
「その時は、彼らはいい人だ、私を殺さなかったからと思うようにいたします。」
「では、刀で彼らがそなたを殺した時は、どうするか?」
「その時は、彼らはいい人だ。世の中には人生の様々な苦悩に押しつぶされ、刀や毒で自らの命 を絶つ者もあります。誰かが自分を殺してくれれば楽になれるのにと願っている人もいます。ですから、彼らは私の命を絶って、自らの命を絶つ労を省いてくれたと思うことにしています。」
「富楼那よ、宜しい。そなたにそれだけの覚悟があるのなら大丈夫であろう。スナーパランタ国へ行ったら多くの信者を得るであろう。」
穿った見方かもしれないが、この繰り返し、この繰り返しの念の入れ方は、富楼那がかつて兄の妻と駆け落ちをした事実をお釈迦さまが知っておられ、世の中はそう甘くない、故郷の町には未だにそのことを知っている人が生きており、思わぬ非難や迫害に遭うかもしれないと心配されたのだとも解釈されている。
さらにまた、この時に富楼那が答えたのは、故郷に帰って過去の罪業を命懸けで懺悔しつつ生きるということではないが、そう読み取るのが正しいという意見もある。
いずれにしても、お釈迦さまはバラモンを初めとする他の宗教者に対して、教義を真っ向から批判し、邪教と決めつけることをされなかった。一旦相手の立場を認め、次第に真の信仰に導く布教の仕方であったと言われる。また、普通に考えれば、お釈迦さまの教えに馴染んでいる王舎城を中心とする都市の人々に教えを説く方が苦労も少なかったろう。しかし、多くの弟子たちは安易な道を選ばずに、生命を賭して辺境の地の布教に旅立った。その時の覚悟をこの富楼那の答えが代弁しているようにも思われる。
スナーパランダに帰った富楼那は、そこで500人の在家信者を教化し、三つの神通力、天眼通、宿命通、漏神通の三明を我が物にして、その後に亡くなった。その時、多数の比丘たちがお釈迦さまの許にやって来て、「富楼那は、来世はどのようになったのでしょうか」と質問した。すると、お釈迦さまは「彼は般涅槃した」、つまり、仏として安らかに輪廻の境を越えたと答えられている。(中村晋也)