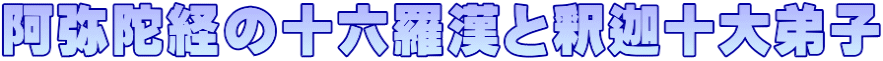
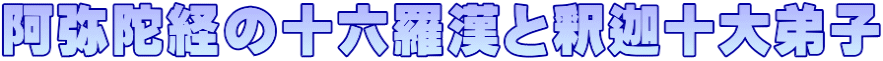
![]()
![]()
 (一)お釈迦さまとの出会い
(一)お釈迦さまとの出会い
須菩提の生れはコーサラ国の舎衛城で、インド名はスブーティ。父のスマナはお釈迦さまに祇園精舎を寄進したスダッタ長者の弟であり、彼は当時隆盛になってきた商業活動によって経済力を蓄えた富裕な一族の子として育った。若い時はわがまま放題で荒れた暮しをしていたと伝えられるが、出家後は心から修行に励み、見事なまでに自らを変えた。
お釈迦さまが祇園精舎に初めて入られた日、彼も伯父の傍らで教えを聞いた。そして深く心を動かされて、即座に出家を志した。
この日、祇園精舎に集まった多くの貧しい人に向けてお釈迦さまが説かれたのは、たとえ金銭も何も持たずとも布施はできるという無財の七施の話であった。即ち、
①にっこり微笑み掛けて人の心を幸せにする「和顔施」
②やさしい言葉をかける「愛語施」
③立ち疲れている人に座る席を与える「床座施」
④やさしいまなざしで見る「慈眼施」
⑤自分の体で人のために何かをする。今ならさしずめボランティアに当たる「捨身施」
⑥何らかの心配りをする「心慮施」
⑦行き暮れて困っている人に宿を貸す「房舎施」
の勧めであったと言われている。
(二)解空第一、無諍第一
須菩提は解空第一として、「空」を説く大乗経典にしばしば登場するが、「空」が分かるというのは、ある点でとても感覚的な人でなければならず、その点で土地を基盤とする伝統的な地主階級ではなく、自由な気風の階級に属したことが彼に利したと言われる。
「空」とは仏教の基本哲学である。人間には色々な物にこだわるから悩みが起きる。だから、一切のこだわりを捨てる、過ぎ去ったことや、どうにもならないことにいつまでも執着しない、偏らない心を説くものである。
次の無諍第一もまた、人と争わない根底に「空」の心がある。お釈迦さまが無諍第一と賞賛されているが、その前提として比丘たちに「諍いを起こさない条件」として七条を示されている。
①欲と結合する楽しみに耽らず、自分の悩みに溺れ ないこと。
②両極端を離れた中道から涅槃を求めること。
③褒め上げたり、他を非難したりせずに法を説くこと。
④色、声、香、味、触の五欲を離れて、内に楽しみを追求すること。
⑤陰口を叩かず、面前でこそこそ悪口を囁かないこと。
⑥緩やかに語り、早急に結論を急がないこと。
⑦各国土の言語にこだわらず、呼称を過剰に用いないこと。
この世は仮のものと思い定めれば、その中で人と競ったり争ったりするのが無意味に思える。せめて優しくしあおう、それが須菩提であった。
(三)頻婆娑羅王と被供養第一
また被供養第一と称された。多くの縁のお蔭で現在あることを感謝し、信者からの供養を誰よりも篤く受けたことで付けられた呼び名であるという。
須菩提がマガタ国の王舎城に遊行して訪れた時、その説法を聴聞して感動した頻婆娑羅王は「私の感動をお伝えするために、須菩提尊者に草庵を造って寄進しましょう」と申し出た。その当時のマガダ国は十六大強国と呼ばれた中でも最大であり、王の仕事は次々にある。そのために王は忙しさに取り紛れ、小屋の屋根を葺くのを忘れたまま彼に寄進したのであった。
一方、須菩提は供養されたものは心から感謝いただくという信条の通り、その草庵に住んだ。いかに南国といっても夜露も降りれば風も吹き抜ける。第一雨が降ったら困る。ところが、須菩提はそう思いもしなかったし、王の役人に屋根を葺いて欲しいと願い出もしなかった。お釈迦さまが、死後のことは死んだ時に考えれば良いと説いておられたように、降ったら降った時のこと、そのように考えていたのかもしれない。ただ、「彼が住んでから一粒の雨も降らなかった」とお経にはある。
困ったのはマガタ国の農民である。雨が降らないので稲も草も枯れた。それで王に何とかして欲しいと陳情に及び、王が役人に命じてその訳を調べさせると、須菩提の小屋に屋根がないのを知った竜神が雨を降らせなかったのだった。自らの失念に気づいた王が、急いで小屋の屋根を葺かせると、旱天の慈雨の言葉通りに雨が降り、人も農作物も生き返った。
屋根ができた時、須菩提は素直に喜んで、一つの詩を作った。『長老の詩』(テーラガータ)に収められている詩の中で、この一詩だけが須菩提の作と伝えられるものである。
私の庵は見事にできあがり、
風も通さず、心地が良い。
天よ、思うがままに慈雨を降らせよ。
私の心は自然の理をよく悟り、何事にも動じない。
私は道を求めてさらに歩む。
天の神よ、どうぞ雨を降らされよ。
須菩提が被供養第一といわれるのは、単に供養されるものが多かったという量の問題ではない。心から与えられた供養を喜び、感謝をエネルギーにして、更なる修行に励んだことによるのである。それだからこそ、須菩提は後に成立する『般若経』の中で、お釈迦さまが「空」を説く相手としてしばしば登場するのである。(中村晋也)