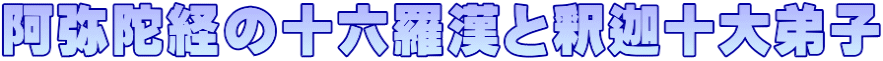
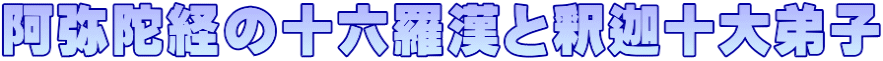
![]()
![]()
 (一)阿那律の出家
(一)阿那律の出家
阿那律、インド名はアヌルッダ。彼の出自についても所説があり、兄弟の間柄も彼が兄という説と、弟という説が伝わっている。ここでは通説に従ってカピラ国の王族の息子で、お釈迦さまの従弟、彼の方が弟としておきたい。
お釈迦さまがカピラ国に何度目かに帰られた時、多くの釈迦族の若者が次々に出家を果たすということがあった。その時、阿那律兄弟の家からは誰も出家していなかったので、どちらかが出家しようと、二人で相談した。揃って出家すれば田畑の仕事が困る。それで兄のマハーナーマンが家に残り、弟の彼が出家することになった。ところが、両親の猛反対に遭う。しかし、幾度となく必死の説得を試みた末に、とうとう母親が妥協案を出した。「一族の跋提(バツダイ)も出家するなら許す」と。跋提は阿那律の友だちであり、既に政治面でも活躍しているリーダー格の青年であった。また、取り分けその母親が愛している自慢の息子だったから、阿那律の母のもくろみは、「あのお母さんが許すはずがない」というところだったろう。ところが、阿那律は跋提の説得に成功した。
こうして7人の若者が一挙にお釈迦さまの教団に入門した。その7人とは、跋提(バツダイ)、金毘羅(キンピラ)、南提耶(ナンテイヤ)、婆咎(バグ)、阿難陀(アナンダ)、提婆達多(ダイバダッタ)と剃髪師の優波離(ウパリ)であったと言われ、提婆達多は後にお釈迦さまに叛逆した人である。
(二)不眠の誓い
ある日、お釈迦さまの説法の座で阿那律は不覚にもウトウトと居眠りをした。場所は祇園精舎の講堂であり、集まった大勢の比丘や信者の中には「何ということだ」と目引き袖引きして謗る者もあった。お釈迦さまは、「気持ちよく眠っている間は煩悩がない。それもまた良いではないか」と、人々の前では阿那律を庇われた。けれども、後で阿那律一人を呼び寄せて、
「阿那律よ、お前は何を求めて出家したのか」
「世尊よ、私は生老病死の四つの苦しみから逃れるために出家しました」
「そういうお前が説法を聞きながら居眠りするとは。最初の決意はどうのか」
「世尊よ、申し訳ございません。今日より以後、私は如何なることがあろうとも世尊の前では眠ることは致しません」
自分の失態を阿那律ほど真剣に恥じた人はいない。彼は睡魔と闘い始めた。程なく目がただれる。お釈迦さまは医師の耆婆を呼んで治療を依頼するが、いかに名医と雖も、「この眼は眠らなければ治りません」と治療の術がなかった。
お釈迦さまは、さらにこう説得された。
「万物は食事によって生きていくことができる。目には眠りが食事であり、耳には声が食事であり、鼻には香りが食事であり、舌には味が食事であるように。阿那律よ、だから眠りなさい。」
「今は睡眠を取ることが耐え難く感じられる。」
阿那律が答えた時、お釈迦さまはそれ以上の説得をやめられた。阿那律は完全に視力を失ってしまった。
お釈迦さまの教えは極端な苦行を否定し、中道によって悟りを開くことを良しとする。阿那律の行為はこれに反するようでもあるが、人にはトコトンやってみなければ見えてこないものもある。それは、理屈を超えたものだ。阿那律は自らの信ずる道を徹底して進み、肉体の目を失うことで、永遠の真理を見る心の眼を得たのである。
(三)阿那律の言行
阿那律は悟りを開いて阿羅漢となった後、お釈迦さまへの恩に報いたいと説法の旅に出て、ある集落に至った。そこには一人の長者がいて、二男一女があった。この女の子が成長してふしだらな行為をし、兄弟には「妊娠したのは禿人(とくじん)に乱暴されたからだ」と偽った。人々は生まれてきた子どもを「禿子」と呼び、母親を「禿子母」と呼んでいた。
この説法の旅で、阿那律はこの家に一夜の宿を借り、禿子母に誘惑されたが神通力でこれを教化した。さらに彼女の兄弟や多数の人々を教化したが、彼は在家者の家に泊ることをしなかった。
*
また、彼はある村はずれにある園林に泊った時、500人の盗賊に遭遇するが、彼らも神通力で教化し、お釈迦さまの元に連れて来て、善来比丘戒、世尊の「善く来た」という言葉により受戒することで出家させた。
その時に、彼は比丘等に今回の旅での苦行として禿子母とのできごとを話すと、一部の比丘が非難してお釈迦さまに告げた。そこでお釈迦さまは、女人と同宿するならば、波逸提(はいつだい)の軽い罪と「与女人同室宿学処戒」を制定された。
*
ある時、ヴァイシャーリーから舎衛城の長者の元に嫁いだ女性が、夫の留守に姑と喧嘩して、本国に帰ろうとしていた。ちょうど阿那律も舎衛国からヴァイシャーリーへ行こうとしていたので、旅は道連れと同行することになった。
後日、家に戻った夫の長者が妻の後を追ったところ、妻と同行する阿那律を見つけ、二人の仲を誤解して彼を殴った。このとき、阿那律が火光三昧に入って神通力で体から猛火を出すと、その長者に善心が生じた。長者は彼に懺悔し、彼は長者のために教えを説いた。
阿那律は僧伽に着いてから比丘等にこの一件を告げた。これを聞いた比丘たちが「どうして一人で婦人と同行したのか」と非難した。また、比丘等はお釈迦さまの元を訪れて、これを報告した。お釈迦さまは比丘等を集め、彼を叱責された後、比丘等に、婦人と同道して村間に到れば、波逸提(はいつだい)の軽い罪と「与女人期同行戒」を制定された。
*
初期のお釈迦さまの教団で、いわゆる法衣は墓場やごみ溜めに捨てられていた布、道端に落ちている布を拾ってよく洗い、綴り合わせて着るのが決まりであり、一人に許されたのは3枚が本来であった。後に教団が発展するに連れて、多くの衣が豪商や貴婦人から寄進されるようになるが、それとても古びれば自分で繕い、汚れれば洗わなければならなかった。
それは盲目の阿那律にとっては中々面倒な仕事だった。そのために、この世では阿那律の妻であり、彼を深く愛し、死後に天に生れたジャーリニーは阿那律の衣が古びた時に美しい天衣をごみ溜めの中に置き、彼に拾わせた。それを舎利弗や目連などにお釈迦さまも加わって大勢で縫い、彼の三衣にしたという説話が生まれている。ある日、阿那律は衣を繕おうとして、針の糸目に糸が通せずに難渋していた。「幸福を願われる方よ、私のために針の糸目を通して功徳を積んでいただけないか」と近づく足音に声をかけた時、その主はお釈迦さまだった。「では私が功徳を積ませてもらおう」、阿那律の耳にお釈迦さまの声は優しく響いた。
「世尊よ、申し訳ございません。私はどなたか他の僧がおられるかと思って言ったことです。」
「どうして私ではいけないのか。」
「世尊よ、世尊は既に悟りの彼岸に到達された方です。この上功徳を積んで、幸福の道を求められる必要はございません。」
「そうではないのだよ、阿那律。私は誰よりも生きとし生ける物たちの幸福を求めている。」
お釈迦さまの手から阿那律の手に長い糸をつけた針が手渡され、彼の心に「生きとし生ける物のために誰よりも幸福を求める」というお釈迦さまの信条がきらりと映し出された。
お釈迦さまが弟子たちから呼ばれた名は、世尊と訳される薄伽梵(バガボン)、優れた聖者という意味の中に、幸福を求める人の意も含まれる。
*
お釈迦さまがいよいよ涅槃に入られると、弟子たちや集まってきた村人の悲嘆は極度に達した。『仏典』には、未だ修行の足りない比丘たちは砕かれた岩のように打ち倒れ、身をよじって泣き叫び、悟りを開いた比丘たちは、これが無常の世の定めであると心に刻んで悲しみに耐えたとある。
その中で阿那律は、その場に居合わせた最高の長老として枕辺に侍してお釈迦さまの涅槃を見届け、身も世もなく泣き崩れる阿難陀を励ましながら供養の仕度を整え、悲泣する比丘たちにお釈迦さまの平素の教えを改めて説き示して一夜を過ごした。
翌朝、阿難陀に命じてマッラ族(クシーナガルの住民)にお釈迦さまの入滅の知らせを届けたのも、天眼で諸天の意向を伺い天冠寺と名づけられていたマッラ族の廟に遺骸を運んで安置したのも、皆阿那律の采配であった。そして、香と華と楽で供養し、いよいよお釈迦さまの遺骸を荼毘に付すという時、導師の阿那律が如何にしても金棺の周りに積んだ香木に松明の火がつかないという事態が起きた。その時、阿那律は静かにお釈迦さまの心を探り、「世尊は大迦葉の到着を待っておられる。それまで薪に火はつかない」と一同に告げた。
お釈迦さまの入滅後3ヶ月が過ぎ、大迦葉の召集で七葉屈での第一結集が開かれた時、優波離と阿難陀が称えたお釈迦さまの言葉を、全員が「意義なし」と認めると、阿那律がお釈迦さまもそれを良しとしておられるかどうかを天眼で見た。阿那律の天眼を最終的な詰めとして、経と律が定まった。
*
クシーナガルの涅槃堂付近から1㎞ほどの所にラーマーバルという饅頭型の大きな塚があり、そこがお釈迦さまの荼毘所と伝えられているが、村の名をアヌルードワ村と呼ぶという。お釈迦さまを慕った阿那律がこの場を去るに忍びないと住み続け、そこで亡くなったことにちなんでの村の名ということである。
*
阿那律は、ある時、比丘たちから「賢い死に方とは何か」と、質問されたことがあった。その時「四禅、四段階の精神統一を成就することである。また、六神通を得、この世にある内に迷いの世界から抜け出すことである」と答えている。阿那律は自身が教えた如く、この村でお釈迦さまの優しさを偲びつつ生き、そして死んだに違いない。(中村晋也)