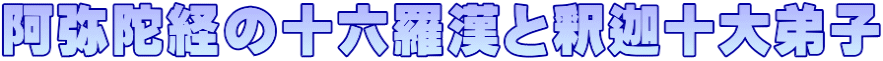
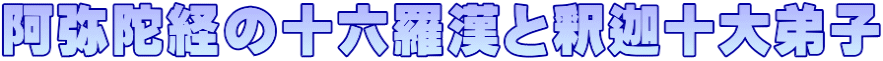
![]()
![]()
バークラ(あるいは波拘羅)は、仏陀が成道する前にヴァンサ国の都コーサンビーの長者の家に生れた。ある日、母が彼を抱いてヤムナー河の川辺に出た時、誤まって水に落とされ、巨大な魚に飲まれた。しかし、奇跡的に彼は魚の腹の中で生きていた。やがて、一人の男がこの魚を釣り上げた。その下流に当たるバーラーナシーの長者の妻がこの魚を買い、自分で料理をしようとして腹を裂くと、中から男の子が出てきた。子宝に恵まれなかった彼女は非常に喜び、我が子のように育てた。これを伝え聞いた川上のコーサンビーの長者の妻は、それこそ自分が水中に落とした子であるから返してくれるよう頼んだ。しかし、川下の長者の妻は承知せず、争ったが決着がつかず、国王の裁定を仰いだ。王は両方の言い分を聞いたうえ「双方の言っていることは、それぞれもっともで、どちらの子とも言い難い。そこで両家の子として養育するように」と申し渡した。そのために、この子はバークラ(両家の意)と名づけられた。
バークラは両家の期待を一身に集めて生長したが、出家を志し、仏弟子となって直ちに阿羅漢果と呼ばれる位に達した。彼は出家してから一回も病気をしたことがなく、長寿をたもち、死期を覚ると「結跏趺坐したままで涅槃に入ろう」と言い、その通りの姿で涅槃に入ったという。自らを厳しく律することに努め、生涯一つの語句も他のために説かなかった。インドの宗教家、行者の一つのタイプを典型的に示す仏弟子である。(菅沼晃)
*
バークラ(波拘盧)は無病第一と言われた。仏弟子の中では一番長命であった。彼は出家して、仏弟子となってから7日間は煩悩が働いていたために在家の信者が供養を申し出ると、そのままそれを受け入れていた。が、8日目に悟りを開いてからは、死ぬまでの間一度も信者の供養した食事を採ったり、仲間の修行者たちに身の回りの世話をして貰ったことはなかったという。
仏陀の時代には、教えを聞いて悟りを開いた聖者はアラハン(阿羅漢)と呼ばれた。アラハンとは「応供」と訳されるように、「尊敬されるべき人」「世の人々の供養を受けるに相応しい人」の意味である。バークラは修行の結果、アラハンの位即ち供養を受けるに相応しい人になったのにも関わらず、供養を受けようとしなかったのである。彼は、アラハンの位に登っても、それで全てが完成したとは思わなかったのであろう。厳しく我が身を律して、供養されたり、他の修行者に仕えたりすることによって、たとえ塵ほどであっても驕り高ぶる心を起こしてはならないと考えたのであろう。
バークラが一生涯、誰に対しても説法しなかったことも、同じ考えに基づいていると見て良いであろう。
インドでは、言葉で説かない布教があるのである。ある経典によれば、仏陀が入滅してから100年たった頃、マウリヤ王朝のアショーカ王(阿育王)が仏跡を参拝する途中で、バークラの骨を収めた塔に詣でたことがあった。その時、案内人が、「この尊者は無病第一で無欲の人でしたが、他人のために一度も教えを説いたことがありませんでした」と言うと、アショーカ王は「バークラは悟りを開いても法を説いて人を救うことができなかったのか」と思って、銭を一個だけ供養した。すると、その塔を守っていた神が、その一個だけの銭をも王に返したという。
アショーカ王は、バークラの無欲さを知って感じ入ったと言うが、「自分は他人の供養を受けるに相応しい存在か」と生涯問い続けたバークラは、ある意味では最も仏弟子らしい仏弟子であったと言えるであろう。
*
仏弟子中で、一番の長寿であったバークラ(薄拘羅)は「無病第一」と言われた。彼は仏弟子となってから、信者の供養した衣を身につけたこともなく、食事の招待を受けたこともなく、堅く身を律して、他の比丘や信者のために教えを説くこともしなかった。
それは、仏陀が王舎城の霊鷲山に500人の比丘たちと滞在していた時のことである。バークラは山の中で古い衣の綻びを縫っていた。天界に住む帝釈天は、古い衣を縫っているバークラの姿を見て、「長老のバークラは悟りを開いてから久しく、煩悩の束縛を完全に離れ、衣食住に執着しないで道を守っている。しかし、一人で静かに修行しているだけで、人のために教えを説かない。まるで異教徒のようだ。この長老は人のために教えを説くことができないのだろうか。私が試してやろう」と思い、バークラの前に姿を現わして言った。
「智者は喜んで法を説くのに、貴方はどうして教えを説かないのですか。煩悩の束縛を離れて悟りを完成していながら、どうして法を説かずに、寂然として沈黙を楽しんでいるのですか」。
バークラは静かに答えた。
「仏陀を初め、サーリープッタ、アーナンダ、マハーチュンダなど、説法に巧みな長老たちがいて、能く法を説いているからです。また、悟りを得た聖者は猥りに口を開かず、静かに黙っているべきであると仏陀は教えているからです。」
これを聞いた帝釈天は、この聖者は人のために法を説くことができないのではなく、仏陀の教えの通りに沈黙を続けていることを知り、満足して立ち去った。賢聖黙然、「聖者は猥りに口を開かず、静かに黙っているべきだ」という教えを楽しんでいたのだ。バークラは、このように誰にも法を説くこともなく、何十年という長い間静かに修行を続け、涅槃の時が近づいたのを知ると、修行者たちに、「各々方、私は座を組んだまま涅槃に入ろう」と言って、その通りに涅槃に入ったという。
*
バークラ(薄拘羅)は、仏弟子中で一番丈夫な身体を持ち、決して病気をせず、長寿を保った人であった。彼がマガタ国の都王舎城の竹林精舎に滞在していた時のこと、在家時代に親しくしていた一人の友人が訪ねてきて、彼に聞いた。
「バークラよ、貴方は仏教を学ぶようになってから何年ですか」
「友よ、80年になります」
「バークラよ、80年の間、貴方は女性との交わりを持っていないのですか」
「友よ、そのように問うものではありません。欲望の心を起こした心があるかと問いなさい」
「バークラよ、改めて問います。貴方は欲望の心を起こしたことがありますか」
今は異教徒の修行者であるかつての親友に、バークラは次のように答えた。
「友よ、塵や垢に塗れた衣(糞掃衣)を身に付けてから80年になります。その間、未だかつて信者が供養してくれた衣を着たこともなく、針を使って衣を縫ったこともありません。信者の食事の招待を受けたこともないし、女性の顔を見たこともありません。また80年の間、一度も病気をしたこともないし、薬を飲んだこともありません。
私は出家してから7日の間は欲望に心を動かされていて、信者の供養を受けたりしましたが、8日目に悟りを開いてからは、欲心を起こしたことも、怒りの心を持ったこともありません。」
異教徒の行者であったかつての友人は、これを聞いて心を打たれ、仏門に入って修行した結果、心の眼を開いたという。
バークラは160歳まで生きたという。80歳で出家して悟り、160歳で涅槃に入ったのである。(菅沼晃)