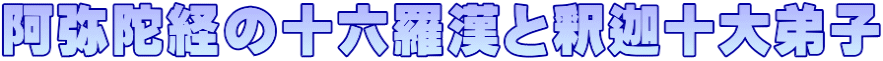
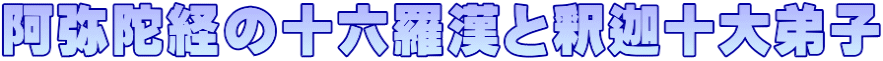
![]()
![]()
漢字に訳して房宿といわれますが、この房宿という言葉で摩訶劫賓那が表わされていることには三つあると考えられています。
この「宿」という字は、中国では星のことを宿と言います。二十八宿とかというのがありますが、オリオン座などの「座」を宿という。また、座も宿の同じような意味でもあります。夜いる場所は宿だし、昼いる場所は座ですから、ポイントというような意味です。
それで、どういう星か分からないけれども、房宿という星です。インドでは非常に星占いが盛んで、摩訶劫賓那のお母さんがこの星に祈りをかけて生れたのがこの人だというので、房宿という。つまりその星のお蔭で生まれてきたので、房宿から生まれたという意味で、房宿と言われているのだと考えられています。それから、第二番目は、非常に星占いが巧みであったから房宿という名がついているということです。宿という字を星として考えるわけです。占星術が非常に巧みであった、占星術に長けておられたというので、房宿と呼ばれていたと言うのです。
それから、もう一つは摩訶劫賓那がまだ仏弟子になられる前に、旅をしておられたら大雨が降ってきた。そこで、近くの焼物師の所へ行って一夜の宿を求められた。その焼物師は快く「どうぞ」と承知してくれた。そして乾いた草を敷いてそれを座にした。そこへもう一人出家者が来られた。その人もまた一夜の宿を請われた。それで同じ部屋に場所を設けて「どうぞここへおいでください」と言って、二人を同じ部屋に入れた訳です。
ところが、後から来た比丘が説法を始めた。摩訶劫賓那はまだ出家していない俗人です。その俗人に対して、出家者である比丘が懇々と説法を始めたのです。ところが、摩訶劫賓那は聞いているうちに阿羅漢の悟りを得たというのです。摩訶劫賓那はその比丘の説法を熱心に聞いたのでしょう。この人はまじめな人ですから、熱心に聞いていたら、そのうちに段々目覚めてきて、遂に阿羅漢の悟りを開いた。そして、実はその後から来た比丘というのは釈尊であったと言われております。それで、いわゆる部屋に宿って悟りを開いたということで房宿と言われると。文字通り宿として受け取るわけです。これが摩訶劫賓那の名の元だというのです。このように、房宿には三つの解釈、考え方があります。古来こういうことが言われているのです。それでこの人は知宿第一と呼ばれています。(仲野良俊)